まさか泣き出されるとは思ってもみなかった。
その涙を忘れる為にも、最後まで隠していて正解だったと胸を撫で下ろす。
鎖を掌に戻された折には驚いたが、つけろとねだられ嬉しくない訳が無い。
こうして幾度でも振り回される。その涙に、笑顔に、言葉一つに。
この世の仕来りを御存知ないのは構わん。訊いて下さればそれで良い。
そして共に居て下されば、それ以外は何も望まない。
弽も蝋燭の灯も、王妃媽媽の豪華な御膳の下賜も、朋の集う宴も要らん。
あなたから天界の言の葉が一つ聞ければ、他に欲しい物など何も無い。
その声で呼び、その笑顔で振り向き、その指でこの指先を握られれば。
その瞳でこの眸を覗き込み、その心を預けてくれればそれだけで。
今日生まれ、今まで生き、今此処に居る理由。
「・・・イムジャ」
細い肩に額をつけ俯いて呼べば、優しい息が髪にかかる。
「なあに?」
俯いたまま伝えたくは無い。細い肩から額を離し、あなたの瞳を覗き込む。
知っている。俺はあなたに逢う為に生まれて来た。
信じている。あなたは俺に逢う為に生まれて来て下さった。
「愛している」
教えて下さった天界の言の葉を口にする度、何故心を抓られるような気分になるのか。
「うん、私も愛してる」
「・・・愛している」
全てを伝える言の葉でも足りぬと思ってしまえば、これ以上俺に何が出来るのだろう。
「うん。私も、愛してる」
娶った後もこれ程欲しいと思ってしまったら、この後はどう心を宥めれば良いだろう。
一体この方は俺にどんなまじないを掛けたのだろう。
身も心も全て俺のものになって下さった方に、これ以上の何を望むのだろう。
王妃媽媽の御膳の下賜も、来年の宴の誘いも、全て頭痛の種でしか無い。
この方が矢面に立つ、事に巻き込まれる、それだけが不安で仕方が無い。
「頼みます。来年の王妃媽媽の宴は、丁重にお断りを」
「だってもう媽媽と約束しちゃったんだもの」
「・・・約束」
その一言に頭を抱えたくなる。
何故俺に尋ねる前に決めてしまうのだと、思わず声を荒げそうになる。
「うん。今年の媽媽の御誕生会もやりたいってお伝えしたら、媽媽がお返しに、来年はあなたと私の誕生日を内輪でこっそり」
「・・・イムジャ」
どうすれば判って下さるのだ、俺のこの方は。
目立たず宴を催すなど、王妃媽媽の御立場では無理に決まっている。
来年も同じ口実では無理がある。王妃媽媽が直々に兵を労うなど前例が無い。
愛しているの言の葉で、総てが伝わるのでは無かったか。
その言の葉を耳にしながら、何故この心は伝わらんのだ。
「今年が最初で最後です」
「だって、誕生日は毎年来るのよ?」
「二人で祝います」
「だって、もう言っちゃったんだもの」
「夏風邪を拗らせます」
「・・・え?」
「来年。拗らせますので、看病して下さい」
嘘も方便だ。この方を厄介事から遠ざけるなら幾らでも使ってやる。
「そんなに困るの?あなたが嘘つくほど?」
「嘘ではなく、方便です」
「どう違うの?」
「偽りか、角の立たぬ断りの口実か」
「すっごい言い訳ね」
あなたは暢気に噴き出しながら、この胸に細い背を凭れる。
「分かった。来年からは2人っきりでお祝いしましょ」
「はい」
「毎年言うわ。どれくらいあなたを愛してるか。今年より来年はきっともっと愛してるもの」
「はい」
「10年たったら、愛してるって一晩中聞かされる事になるわよ?」
「構いません」
愛してる。愛してる。繰り返される甘い声。
それだけが聞きたかった。それさえ聞ければ何も要らん。
俺の今宵の望みはもう充分過ぎる程に叶えて頂いた。
「みんなとパーティした方が楽しくない?ヨンアお酒好きなんだし」
「いえ」
夜が明けるまで二人きり、この耳で飽く程聞きたい。
そしてあなたに感謝し、この口で飽く程お伝えしたい。
「三十年経てば、三日三晩聞けますか」
「聞きたいの?」
「はい」
「じゃあ言うわ。途中で居眠りしたら許さないから」
「しません」
川風に揺れる蝋燭の灯の中、細い指がこの指先を探す。
先に握れば嬉し気に握り返され、指先は紅い口許へ寄せられる。
「聞き飽きたなんて言わないで。ずっと聞きたいって思っててね」
「はい」
温かな息がかかる指先で、あの紅い唇を辿る。
此方へ背を向け顔は見えずとも、その形で微笑んでいるのが判る。
その唇で囁かれる度、慾は深くなる。
聞きたい。一晩でも三日三晩でも、そして出来るなら息の終まで聞いていたいと。
此度はようやくこの心が伝わったらしい。
辿った指先に触れたままの柔らかな唇が、伝えるように確かに動く。
声にせぬからこそ尚の事、心に真直ぐ響く想いを。
愛してる
「大護軍!ここにいたんですか!」
「散々捜したぞ、何でこんなとこにいるんだよ!」
唇だけの囁きの最中、蝋燭の灯の外。
河原の石を踏み駆け寄る幾つもの乱れた足音。
舌を打ち唇から指を離し、近寄る気配からこの方を背で隠して立ち塞がる。
馬に蹴られて一度死んでみるか、この酔客共が。


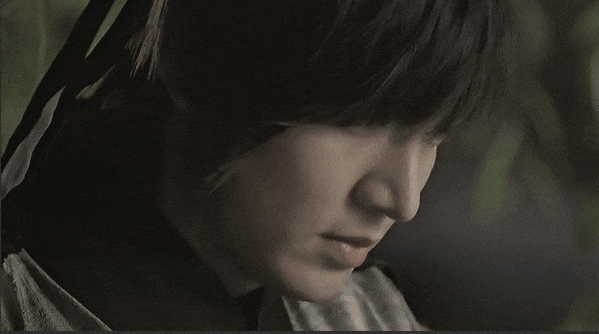



コメントを残す