「そして、医仙」
「・・・はあ?」
突然他人行儀に自分を呼ぶヨンの声にウンスが顔をしかめる。
「医仙に一つ、伏して願いを」
「なぁに。何なのよ」
「此度敷き直した陣の最も肝要な事です」
卓向うで姿勢を改め背を伸ばすヨンに、ウンスはじっと目を当てる。
「うん。何」
「その口、お閉じ下さい」
「・・・はい?」
「さすれば俺が叔母上とチュンソクとどうとでもします。ですから」
ヨンの声にチェ尚宮が重々しく頷く。チュンソクがウンスをじっと見る。
「ですから医仙はお黙り下さい。宜しいですか」
その声にウンスは頷いた。
「判った、もうしゃべんなきゃいいんでしょ」
「はい」
絶対に無理と判りつつ、ヨンは深く頷いた。
何よりだ。碧瀾渡へ、そして天門へ。
この暫しの平穏な時に、可能な限り開京を離れる。
離れればこの方が叫ぼうと喚こうと、開京へまでは届くまい。
「さて」
チェ尚宮の声に、三人の目があたる。
「明日より碧瀾渡だな。万一事あらば即座に戻って来い。良いな」
「ああ」
「では私は行く」
「判った」
「医仙」
「はい、叔母様」
「此度は曲げて、この男の言うとおりに」
「・・・はい」
最後の声にウンスが頷くと、チェ尚宮は微笑んで柱から離れ、私室の階を上がり、扉向うへと姿を消した。
「では大護軍。自分も」
チュンソクが卓の二人へと頭を下げ、最後にウンスへ体を向ける。
「医仙」
「判ってる、しゃべんない!」
「何卒くれぐれも、宜しくお願い致します」
「はーい」
その返事に頷くとチュンソクは階を駆け上がり、扉を押して抜けた。
「さて」
二人きりの私室の中、ヨンは卓向かいのウンスへ言うと席を立った。
ウンスがそれにつられたように椅子の音を鳴らして続く。
「典医寺へ参りましょう」
「いいわよ、まだ明るいじゃない。1人で」
「いえ」
先に立ち私室を抜けながら、ヨンは首を振る。
「キム侍医に話があります」
******
「碧瀾渡」
典医寺でチェ・ヨンと向かい合うキム侍医が頷いた。
「ああ。それ程長くはかからん。
が、今後幾度かこの方は、医寺を抜ける事になる」
「判りました。此方でもその心積りで準備を」
「王妃媽媽の御体には問題ないか」
「ええ。私も、他の医官もおります」
「頼む。婚儀が終われば落ち着こう」
「お任せください」
「徳興君はどうだ」
ヨンは心に掛かる問いを投げる。
あの後どうなったのか。見舞うつもりなど当然毛頭ない。
但し死なせる訳にはいかぬ。生きてこその切り札だと。
「ウンス殿の治療の甲斐あり、死んではおりません」
その平静を装った声に、ヨンはキム侍医の目を覗き込む。
「キム侍医」
「はい」
「死んでおらぬと、生きているは違う」
「おっしゃる通り」
キム侍医はようやくその目許を綻ばせる。
「徳興君さまは、死んではおりませぬ、チェ・ヨン殿」
一言ずつゆっくりと意味有りげに区切るキム侍医の声にヨンは頷く。
「・・・成程な」
「深手でしたので、肉が上がるまでにはもう暫し。
しかし私の鍼も、ウンス殿の手当ても功を奏しております。
チャン御医の残して下さった処方の薬も、大層効きがよく」
「・・・そうか」
ヨンは典医寺の窓の外、傾ききらぬ夏の陽に光る庭へ眸を投げる。
此処に来るたび、未だにお前の気配を感じる己はおかしいか。
お前は彼岸からも、こうして尽力しておるか。いい加減に少し休めば良いものを。
あの飄々とした面で駆けまわるこの方を助け、焦る俺に薄笑いを浮かべておるか。
お前にも参列してほしかった。
この方の医術に惚れ込んだお前にこそ、参列してほしかった。
なあ、侍医。
典医寺を出たヨンとウンスが並んで歩く皇庭の隅。
夏の陽がこれ程長いなど、そしてこれ程暑いなど。
「この夏は」
ヨンの小さな声に、ウンスがその顔を見上げる。
「暑いです」
「そうね」
忘れていた。この方にもう一度逢うまで。
戻って初めて共に過ごす夏が、これ程暑いなど。
そうだ、夏は暑い。冬は寒い。春には花が咲き、秋には葉が散る。
あの丘で待っていた筈が。春も、夏も、秋も、冬も待っていた筈が。
この方が戻り、じきに二度目の秋が来る。
その時には想うだろうか。あの黄色い花を見て、思い出すだろうか。
どれ程待っていたか。どんな秋だったか。
遥か彼方のようでいて昨日のように苦しくて。
深夜の寝台で闇の中、弾かれるように眸を開けて、腕の中の小さな息に安堵する。
そんな事も次第になくなっていくのだろうか。
横に感じる温もりと寝息に馴れいくだろうか。
在るのが当然と思い、忘れていくのだろうか。
それほどまでに馴染めるならば、それもまた一つの倖せか。
何時でも其処に在る事が、当然と思えるようになるのなら。
姿を見るたび声を聞くたび、傍に寄るたびに胸が痛くなる。
そんな気持ちが薄れていくならば、楽になれるのだろうか。
判らない。判らないとヨンは首を振った。
「・・・伺っても」
「なぁに?」
「何故、王妃媽媽に金剛石の話を伏せたのですか」
ウンスならば必ず話をする、話していて当然と諦めていた。
しかし宝玉工の水晶や翡翠の薦めに逡巡なく頷いた王を見て以来、ヨンの頭に疑問が残る。
ご存知ならば、必ず金剛石をと言うはずだ。
それをすんなり翡翠や水晶などで良いなど。
「何故黙っておられたのです」
「私は喋っちゃ駄目なんでしょ?」
「イムジャ」
「だって、邪魔者扱いされたし」
口を尖らせ拗ねた声で呟いた後に、気を取り直すように
「でも今回は、許してあげる」
ウンスはヨンへ大きく笑った。
まるで花のように。明るい夏の陽のように。
「この時代はきっとダ・・・金剛石より翡翠とか水晶の方が、高級品なんでしょ?違う?」
「それは、まあ」
確かにそうだとヨンは頷く。
己でも確かめるまで、金剛石が一体何の役に立つのかすら考えたこともなかった。
ただの硬い石だと思っていたほどだ。
「二人だけが知ってる秘密があってもいいじゃない」
ウンスは楽しそうに言って、横を歩くヨンの手を取った。
そこに嵌められたままの金の輪に指先で愛おしそうに触れながら、
「媽媽と王様の愛の深さは、私は知ってるからいいの。
石なんて関係ないくらい、愛し合ってるお2人だから」
そのウンスの物言いに、ヨンの歩みが遅くなる。
繋いだ手を引く格好でウンスは足を止め、いつの間にか歩を止めた後ろのヨンへ振り返る。
「なに?」
「それは」
左手をウンスに取られた格好で、ヨンはその場で問い正す。
「俺とイムジャには金剛石が必要で、王様には御不要と」
「は?」
「そういう事ですか」
「ちょっと、どうしたのヨンア」
「俺達には割れず欠けず曇らぬ石の助けが要るが、王様と王妃媽媽にはそんな事は御不要と」
ぷ。ウンスはヨンの声に、堪らず噴き出した。
「そんなわけ、ないでしょ!」
左手だけを掴んでいたウンスは、立ち止まるヨンへ一歩寄る。
寄って残った右手も取り、その大きな両掌を自分の小さな両手で出来るだけ包み込むように、祈るように握りしめる。
この手から心が伝わればいいのにな。
私たちが一番素敵なカップルよ。いつだってそう思ってる。
もちろん周りのみんな素敵だけど、でもやっぱり私たちが最強よ。
あなたが判ってくれればいいのにな。
ちょっとだけ私たちの秘密があってもいいじゃない。
誰も知らない2人だけの秘密が、1つくらいあってもいいわよね?
首を傾げるウンスを、西からの夏の陽が染め上げる。
その緋色に染まる髪を、胸が痛むほど懐かしく想う。
慣れる事など、永遠に無理なのだろう。
石があろうと無かろうと変わる事など端から無理だ。
厄介だ。手が掛かる。眸が離せない。気を揉ませる。
覚えてもらわねばならぬ事も、教える事も多すぎる。
だからと言って、楽な女を選ぼうなど一度でも思うたか。
この方を知って以来、他の女が眸に入る事など一度たりとてあったか。
共に年月を重ね、互いに皺だらけになろうと。例えこの方の足腰が立たなくなろうと。
どれ程の富を得ようと、全て捨て漁師になろうと。
幾度己に問い直しても、返る答えは変わらない。
「石の事は2人の秘密にしたかったの。この世界ではまだ誰も価値を知らない。
私たちだけが知ってる。それでいいじゃない」
肩を竦めて笑うウンスに、ヨンはゆっくり目を細めた。
皆さまのぽちっとが励みです。
お楽しみ頂けたときは、押して頂けたら嬉しいです。
![]()
にほんブログ村
今日もクリックありがとうございます。




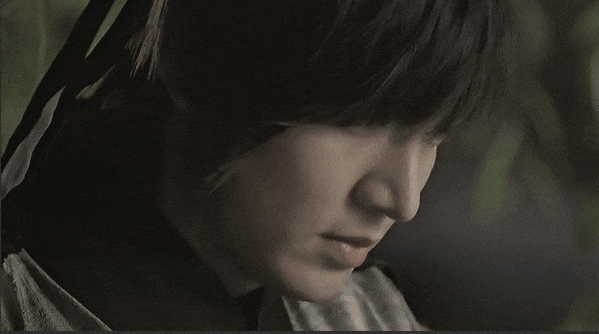


コメントを残す